
今回は佐賀県多久市で作陶されている陶芸家 水谷智美さんを訪れました。最近では、海外からの個展や企画展のオファーも増え、「世界のベストレストラン50」で5度の世界1位獲得などの華々しい実績と、その先見性・独創性で世界にその名を轟かせている「noma」が昨年京都で行ったポップアップレストラン「noma kyoto」でも採用されたりと、活動の幅を広げています。そんな水谷さんに、今までとこれからのお話をうかがいました。
水谷智美さん @tomomi_mizutani
愛知県立芸術大学陶磁専攻卒業。岐阜県飛騨市、島根県松江市での制作を経て、現在は佐賀県多久市に工房を構える。陶器と磁器の中間の性質を持つ土を焼き締めて作る炻器(せっき)を制作。個性豊かな表情の質感と造形を持つ作品を数多く生み出している。
自然と人の、間にあるもの。

陶芸家である水谷智美さんは佐賀県多久市に自宅兼工房を構え、ヨーロッパではストーンウェアと呼ばれる陶器と磁器の中間のような石のように硬い焼きもの、炻器(せっき)の生活道具やオブジェを制作しています。水谷さんの代表的な作品は、主に炻器の表面に色彩を施して、薪窯の灰かぶりのように焼き締める方法で作られています。そうすることで、表面が石や岩のようにざらざらとした質感となり、まるで発掘された土器のような、風化した石のような独特の風合いがでるのです。この焼き締めのうつわを発表した当初は、釉薬がかかっていないことを心配な方が多かったようで、「これは、本当に料理をのせて使えるの?」という質問も多くいただいていたんだそう。水谷さんのうつわは、使い続けるほどに表面のざらつきが丸くなり、油分や色が移っても、それが馴染んで味わいにもなるので、楽しんで育てていただけたら!
昔から『土を焼き締める』ということに、とても魅力を感じているという水谷さん。岩肌に似たざらりとした質感や出土品のような独特の風合いは、うつわの表面に色彩を施して窯で焼き締めることで生まれるもの。やわらかい素材が窯の中で、熱のエネルギーで焼き締まり石のように変化することが、自然の流れをタイムスリップするような不思議な感覚なのだそうです。


自身の手に馴染む身の回りの素材から、自然が秘めている力強さを引き出す水谷さんにとって、焼きものとは自然と人の暮らしの間にあるもの。
「焼きものには、自然から生まれる素材の恵とエネルギーが詰まっています。常日頃から、道具を作ることで、自然と人を繋ぐ役割の1つを担いたい想いがあるので、今よりもさらにニュートラルな気持ちで制作に向き合っていきたいです。道具と人間の関わりって少し呪術的というか……人間は自然の中の一部であると思うし、道具を作ることは人間にとって行為であって、得てしまった本能であるし、力であると思っています。それと自然界のもののつながりというのは、本当はパソコンだって車だって自然界からの恵みだと思います。でも、少し分かりづらいじゃないですか。私の作っているものは、同じものを作る作業でもわかりやすいですよね。ダイレクトに大地から土をいただいて、自ら触れられる素材だけで物をつくるということが理想ですね。」
自然と、繋がっていくもの


水谷さんの作品は手捻りと型打ちで作られていて、土が持つ、ありのままの素朴さの力強さを活かした表情豊かなところが特徴です。大きさや形、色合いは2つとして同じものはなく、それぞれが放つ個性におおらかさが感じられます。そして、厳かながら大きな存在感を放っているのがオブジェたちです。さまざまな大きさや形の四つ足の台や植木鉢、祠など、その種類は多岐に渡り、その時々でギャラリーやテーマに合わせて、インスピレーションのままに自由に作られているように感じます。
「古くから続く人々の暮らしをリスペクトし、これからの暮らしを表現する」というテーマの企画展に参加した際に、古民具の鍬からインスピレーションを受けて色々と試しているうちに、この焼き締めのシリーズができたといいます。このシリーズができた当初はオブジェなどの大きな物を作ることが多かったそうですが、ギャラリーから食器のご依頼が多くなり、食器の制作に力を入れていたところ、自分でも驚くほどに多くの方々に見ていただくようになったといいます。「使っていただくことで、意識をしなくても、自然と繋がれるきっかけになれば」。
大地からいただく、土のちから

水谷さんは、唐津の土に惚れ込んだ、夫で陶芸家の水谷渉さんと共に今の場所に移り住みました。夫の渉さんは唐津で修行をし、唐津焼の作家として活躍していますが、もともと粘土を購入していた粘土工場の社長が高齢を理由に店を閉めると聞き、工場を引き継ぎ、粘土屋としても活動をされています。
「主人は、先代の粘土屋さんから『粘土屋はそんなに一生懸命にやらずに、自分の土を確保するつもりでやればいい』という温かいお言葉をいただいたんです。工場を引き継いだら色々と教えていただけるということで、作家として活動するにしても勉強になるのではないかと決意をしました。先代の粘土屋さんは、作家さんから『こんな土が欲しい』と依頼を受けると、販売はせず、土のある場所の地図を渡してくれたり、良い土が取れた時には作家に配り歩くような優しい方だったそうです。この方が土を融通されたからこそできた作品がたくさんある、というような歴代の唐津の有名陶芸界を支えていたレジェンドのような方でした。ただ、高齢になり、夏場は暑いし粘土は重くてきつかったんだと思います。引き継いだ時は84歳でした。」


「唐津焼の作家の方々は、基本的に自分で土を掘って粘土を作っていると思います。ただ、それだけだと調合が難しかったりすることもあるんですよね。大量に作られる方は、毎回自分の土だけをブレンドして粘土を作るのは大変なので、買い足しのような形で注文があります。主人も安定して取れる場所や、工事現場で出た土などを買い取ってきて、自分用も含めて確保している感じです。」
水谷さんも、夫の渉さんと度々一緒に土を掘りにいくことがあるそうです。渉さんは野生の勘がとても鋭いそうで、「目星はつけているし、分かってはいるんですが、現地でこっちにありそうだ!となると2人でわーっと走っていきます。アドレナリンが出まくる感じです。大きなリュックサックや袋をいくつも持って、山盛り詰めて帰ってきます。」とお二人の土への想いの強さがわかるエピソードをいただきました。
日々の暮らしと、これから
水谷さんが作品に使用する土は、渉さんが採ってきた唐津の土と天草陶石などの磁器の土を混ぜ合わせて作っています。作品によって土のブレンドの比率を変えて作っているそうですが、佐賀のこの土地に住み、作陶することはとても大きな利点があるといいます。「やはり佐賀県で作陶するというのは、アトリエの近くに原料が豊富にある、それがなんと言っても強みです。素材である土の力が圧倒的だと常に思い知らされています。」
窯に入れた時点で作品は作り手の作為からは離れていくもの。あとは自然に任せて、焼き上がった物を受け入れるだけなんだと感じています。」自然を受け入れるとはいえ、少しずつ調整していくのがまた楽しいのだとか。


ここ、佐賀県に移り住んだ時にも、そんな試行錯誤の日々があったそうです。それまでは薪窯で作品を作ってきましたが、子育てなどのライフスタイルの変化のために、労力のかかる薪窯での焼成を続けることを断念し、思い切って電気窯に切り替えました。薪より電気の方がコントロールもきくし、ロスも少ないけれど、薪で焼くことで生まれる風合いが好き。この両方の良いとこを取り入れようと何度も試してはやり直し、納得できるものへと近づけていったといいます。
「土や薪などの原料を自分で準備して、文明の利器の恩恵を受けずに自然の力だけで焼きものを作ってみたいという憧れもあるけれど、そうなると生活は制作中心にしなければ難しいですよね。自分たちの暮らしと作品の制作、どちらも大切にしたいからその時その時でバランスをとりながら、楽しく自分らしい方向性を探っていければと思っています」。
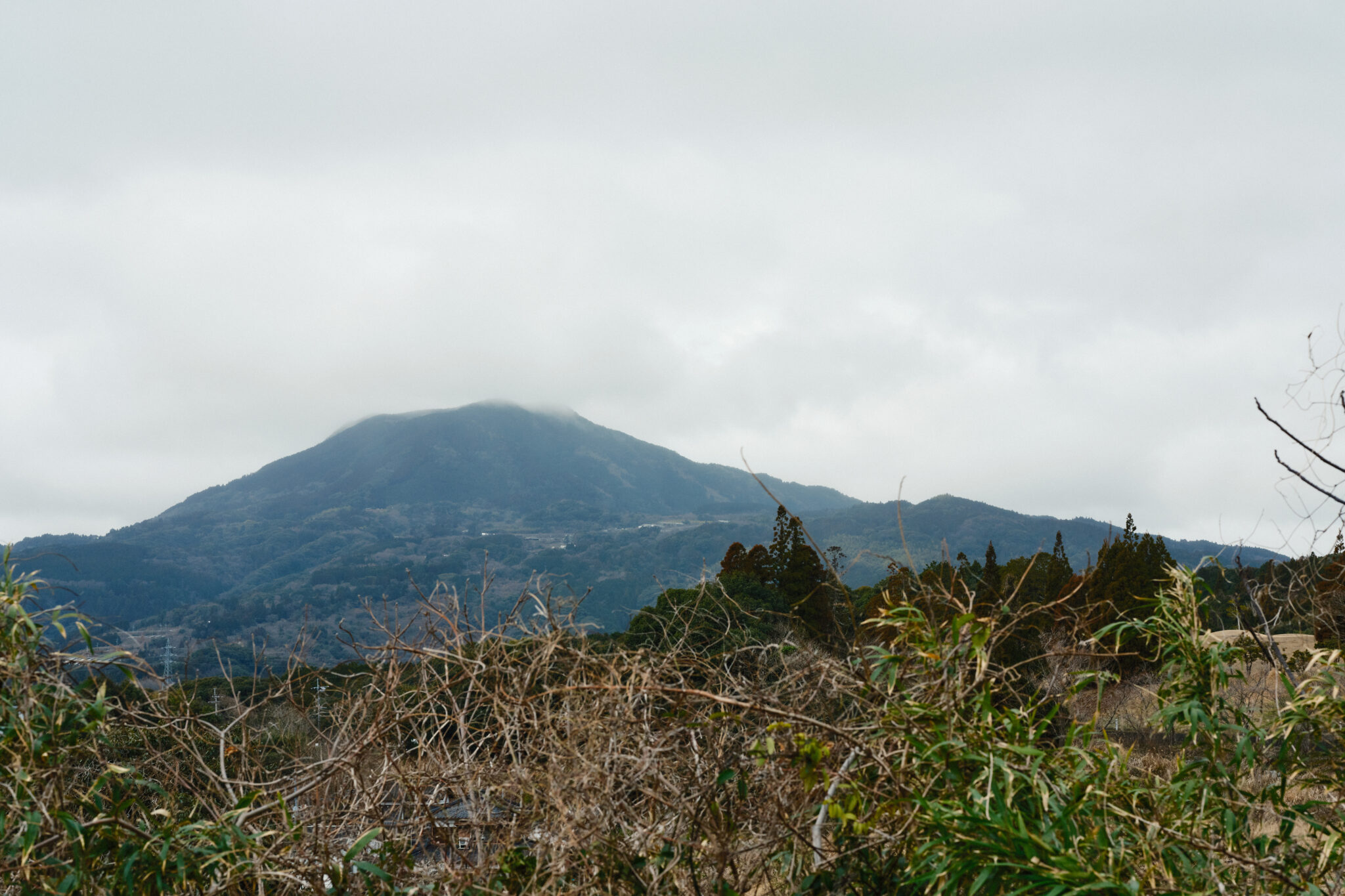

「今、自分の好きなものだけで個展をするとしたら、何を作りますか?」と水谷さんに質問をしたところ、間髪入れずに「薪窯に戻ります」との返事が返ってきました。「人が生きていく中で、昔からある素材を使って道具にしていくことをし続けていきたい、願望は大きいけれど、子育て途中と環境のこともあり、すぐに取り掛かるのは現実的に難しいので、まずは趣味で作ってみようと思います」と目を輝かせながら話してくれました。まだ内緒にしておいて欲しいと言われたので記せないのですが、野焼きをしたり、昔の甲冑のような作りなど文献を読んだりしながら想像を膨らませているそうです。
行方ひさこ @hisakonamekata
ブランディング ディレクター
アパレル会社経営、ファッションやライフスタイルブランドのディレクションなどで活動。近年は、食と工芸、地域活性化など、エシカルとローカルをテーマにその土地の風土や文化に色濃く影響を受けた「モノやコト」の背景やストーリーを読み解き、昔からの循環を大切に繋げていきたいという想いから、自分の五感で編集すべく日本各地の現場を訪れることをライフワークとしている。2025年より福岡県糸島市にて「科学の村」をつくるため、学術研究都市づくりに参画。阿蘇草原大使。
Interview & text Hisako Namekata
Photo by Hideki Mizuta












